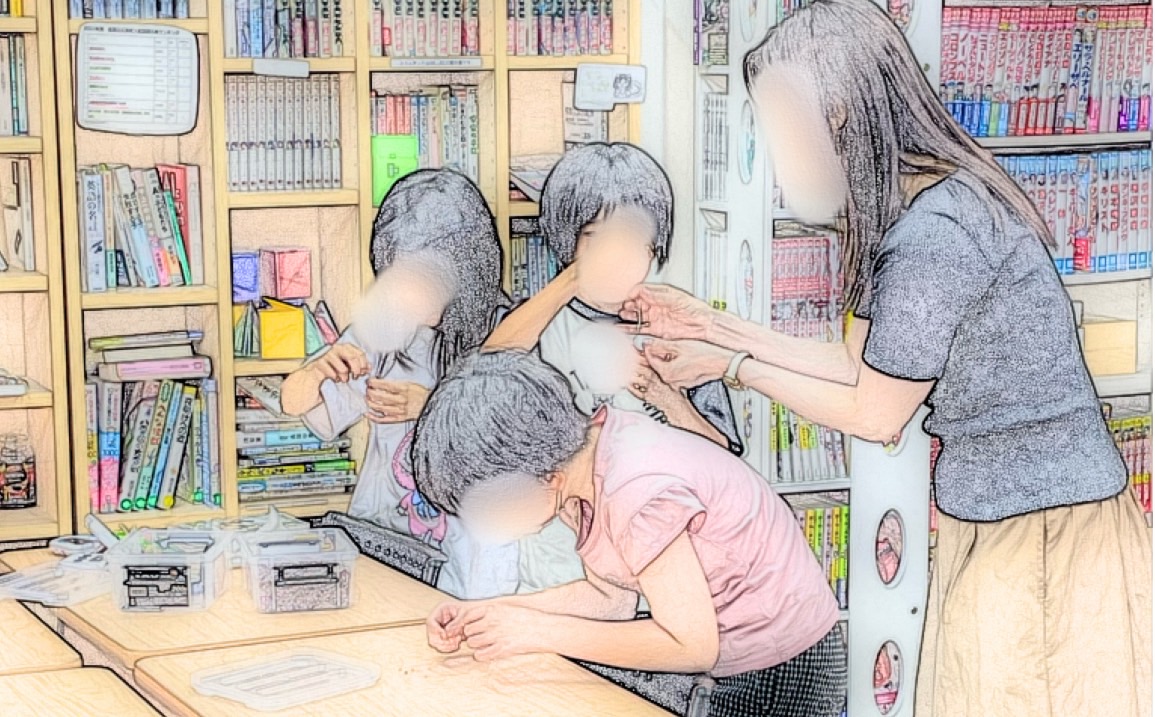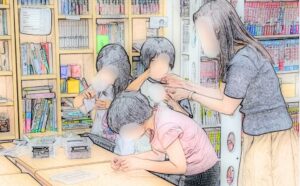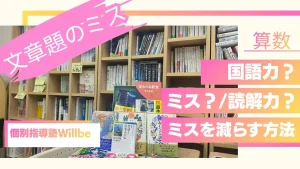本日は、集中力をどうやって鍛えるべきか?学校の宿題に意味はないのではないか?といった小さいお子様をお持ちの保護者様のお悩みに、幼児期に鍛える手先の力といった低学年の間に学習基盤として大切なことをお話ししてまいります。
大した内容ではなく、当たり前のことで、日ごろ同じようなことをお伝えしております。「当たり前」を改めて言葉にするまとめ記事だと思っていただければ幸いです。
目次
幼児期にこそ育てたい“巧緻性”という土台
幼児教育には昔から言われ続けている言葉があります。
「手は外に出た脳である。」
「指は第2の脳である。」
私はこの言葉を、教室で子どもたちを見つめる中で何度も実感してきました。
塾という場所にいると、どうしても「勉強ができる・できない」に視線が向きます。「出来る/出来ない」を見ても何も変わりません。それが、もともとは中学生を対象とした塾でありながら、今では年長さんや小学1年生のお子様まで指導するようになった理由の1つです。
しかし、本当に見なければいけないのはもっと根っこの部分です。
この3つは、すべて 指先の巧緻性(こうちせい) と密接に結びついています。
指先の巧緻性とは何か
「思考の細かさ」をつくる力
巧緻性とは、
指先を思い描いた通りに、正確に、繊細に動かす力です。
具体的には、
- ボタンを留める
- 箸を持つ
- ハサミで切る
- 折り紙を折る
- 積み木をそっと重ねる
- 筆圧を調整して文字を書く
こうした日常の動作ひとつひとつが、実は脳と深くつながっています。
幼児教育の世界では
「手を育てることは、脳を育てること」
と言われるほどです。
集中力は“耳”とも深く結びついています。 👉 幼児期の「聞く力」についてはこちらの記事で詳しく書いています。
耳を良くすれば頭がよくなる|幼児期にこそ鍛えたい“聴く力”の育て方
幼児期に「聴く力」を育てることは、100マス計算やドリルより大切な学習の土台です。スマホ・動画に依存せず、耳と目を集中させる習慣の作り方を紹介します。赤穂市の進…
指先がよく動く子は、総じて 集中力が長く続きます。
一方、巧緻性が弱い子は、途中で飽きたり、雑になったり、注意が持続しません。
これは性格や生まれ持った能力という側面もありますが、大半は、経験の差 です。
なぜ指先が集中力とつながるのか
科学的にも、教育現場でも“同じ答え”になる
細かい作業をする時、脳の前頭前野(集中・思考・判断をつかさどる場所)が活発に働きます。
つまり、
手が育つ → 脳が育つ → 集中力が伸びる
という、とてもシンプルな関係があります。
実際にWillbeでも、指先が器用な子は——
- 図形の理解が速い
- ノートが丁寧
- 読み飛ばしが少ない
- 計算の処理が整っている
- 思考がきれいに整理できる
こういった特徴が現れます。
反対に、手の経験が薄い子は、学習のさまざまな場面で“つまずき”が生まれます。
巧緻性が弱い子に起こる“学習上のつまずき”
あわせて読みたい
身体の発達と算数【非認知能力】指先の巧緻性
本日も張り切って参ります。赤穂市の進学個別指導塾Willbeの光庵(こうあん)です。幼児と算数というテーマから本日は、「身体の発達」「算数」「指先の巧緻性(器用さ…
以下は、実際に現場で頻繁に見られる例です。
① ひらがなの形が整わない
筆圧コントロールが苦手で、線が震えたり丸がつぶれたりします。
② 図形認知が遅れる
図形は「見て・触って・作る」ことで理解が深まります。
手を通さない子は、イメージが育ちません。
③ 作業が遅い・飽きやすい
細かい動作が苦手だと、途中でイヤになりやすくなります。
④ 姿勢が崩れやすく、疲れやすい
手が疲れる → 姿勢が崩れる → 集中が切れる、の悪循環。
⑤ ミスが増える
「めんどう」以前に、“動作そのものがしんどい”ためです。
どれも性格ではなく、手の経験不足 が原因のひとつです。または、手の経験不足が性格を形成しているとも言えます。
ただ、指先の巧緻性を鍛えれば、すべからく”天才”になるとは申しません。
現代の子どもたちが巧緻性を失いかけている理由
スマホ時代の“手を使わない幼児期”
今の子どもたちは、
「目は忙しいけれど、手は働いていない」という状態にあります。
画面を見る時間は増えましたが、
手で何かを“作り出す”体験は激減しています。
昔の子どもは、
折り紙をし、泥団子を作り、紐をむすび、石で遊ぶ生活の中で自然と巧緻性を育てていました。
今は意図的に手を使わせなければ、巧緻性は育ちにくい状況なのかもしれません。
PRESIDENT Online(プレジデントオ…
中学入学時にスマホを買い与えると脳の発達が小6で止まる…スマホを毎日使う子を3年間追った衝撃の結果 小6…
スマホを使い続けると、成長期の脳はどうなるのか。小中学生がスマホを使うことの影響を調べてきた榊浩平さんは「インターネットを毎日使っている子どもたちは、3年間で脳…
家庭でできる“巧緻性トレーニング”5選
お金はかからない。必要なのは時間と手間だけ。
以下は、どのご家庭でもすぐに取り入れられる内容です。
① 折り紙(特に細かい折り箇所)
折り込みや小さな三角を作る作業は、最高の指先トレーニングです。
② 紐通し・ビーズ通し
穴に通すだけで、指先の精度が高まります。
③ ちぎり絵(紙を破る・丸める)
力加減の調整、形状認知、集中の持続。お子様が紙を無作為に破って散らかした場合、許容する心は大切なのかもしれません。