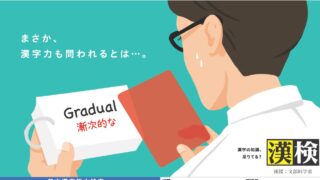今日もブログを読んで下さってありがとうございます。進学個別指導塾Willbeの光庵(こうあん)です。
さて、今月も兵庫県赤穂市の個別指導塾がお届けする圧倒的不人気シリーズ「今月の追加図書」っ今回は「荘園」(中公新書、伊藤俊一、2021)です。
今回も完全に私の趣味です。
荘園を理解すれば日本史が分かる
高校日本史の先生たちの間では「荘園を理解もしていないのに日本史を語るな」という言葉があるそうです。日本史を幅広く趣味としてちょろちょろ勉強している私としては、、、中学生に社会を教えていることに若干の抵抗があります。「荘園を理解もしていないのに日本史を語るな」のせいです。
確かに荘園って分かりにくくて「律令/公地公民」→「荘園」→「戦国時代」という流れはあまりつながらないんですよね。おおざっぱに「知行国から封建制への変遷」といったように雰囲気として理解しても良いのですが、なかなかに分かりにくい荘園です。
戦国時代マニアとして日本の中世のダイナミズムを話す資格はない気がするのです。
そこで、
たまたま赤穂は赤穂書房に立ち寄った際に目に留まった「荘園ー墾田永年私財法から応仁の乱までー」です。
荘園ー墾田永年私財法から応仁の乱までー
荘園は日本の原風景である。公家や寺社、武家など支配層の私有農園をいい、奈良時代に始まる。平安後期から増大し、院政を行う上皇の権力の源となった。鎌倉時代以降、武士勢力に侵食されながらも存続し、応仁の乱後に終焉を迎えた。私利私欲で土地を囲い込み、国の秩序を乱したと見られがちな荘園だが、農業生産力向上や貨幣流通の進展に寄与した面は見逃せない。新知見もふまえ、中世社会の根幹だった荘園制の実像に迫る。
https://www.amazon.co.jp/
私、平安時代周辺のジョウセイにヨワインです。
だから、
「秦河勝」を読むにも苦労したのですが、「荘園」も私を苦しめました。6時間ぐらいかけて半分ぐらい読んで心が折れそうになりました。
本気出して読もうと「トキシラズ」に行ったのにも関わらずっです
私の感想
誰に勧めるべきか?
誰にも勧めません。
「空前絶後のワンちゃん高校生が読む!」を期待してひっそりとWillbe図書館に忍ばせておきます。
もし「荘園を理解してないのに日本史を理解したつもりになるなよ?」というパワーワードに心がザワツイタ方がいらっしゃれば是非笑
戦国大名と組織の近代化
戦国大名という言葉が正しいのかどうか分からないのですが、戦国大名が生まれた背景や下剋上がなぜ起こったのかということを理解するためにも「荘園」の理解が必要です。
戦国大名へとなりかけた地方領主たちが、家臣団をまとめ上げる内部統制を近代的な組織に変えていくことがいかに大変だったのかというものが明るく見えてきたような気がいたしました。
毛利元就がなぜすごかったのか?逆に毛利元就の闇と言うのでしょうか。
聖徳太子の時代。
近代的な中央集権を目指して中国を参考に律令制度が発展した。
ところが、奈良時代の天然痘復興のため、仏教信仰の財源のため墾田永年私財法が生まれ、貴族や自社による荘園が生まれた。
その裏で、天災がながく続き律令制を基盤とした古代村落が解体し郡司を務めていた古代豪族が力を失う。
平安時代。
摂関政治が全盛期の頃、朝廷は国司に権限を委譲して新しい時代に対処をしようとした。公地公民のもとで収穫量と税が上がらず天災に対処できなかったことが原因なのだろう。
税と食べ物を増やしていきたい国司は国内の耕地を有力農民の農業経営と税を請け負わせ、耕地の開発を奨励し開発者に所有権を認めた。さらに開発者には減税というインセンティブを与えた。減税された土地の一部が寺社に寄進/買収され、その一部には政府が介入できないような「不入の権」を認めた。天災に対応するための苦肉の策であったのかもしれない。
しかし、このころはまだすべての土地は朝廷のものであるという考え方が主流であったため、特権的な荘園に歯止めをかけるような令が発布されていた。
白河上皇のころまでは荘園に歯止めをかけようとしていたが、白河上皇は院政を権威づけるために寺社を建設し維持する必要があった。その財源に荘園が使われた。白河上皇が荘園制度を進めていった。後白河上皇の頃には、巨大な荘園群が形成されて社会の基幹的制度になった。
ところで、
ここまで読んでも「不入の権」について、よく分からない点がある。
朝廷が土地の所有権や課税についての認可権を徐々に国司に移譲したから国司の権限が重要になったきたと頃までは良いです。しかし、なぜ土地の所有権や課税についての認可権を国司に移譲する必要があったのかピンとこない。
賄賂??なのだろうか??
どういう荘園やどういう土地が優遇?されるかについては朝廷が決めていたはずです。土地の調査や減免すべき事情や理由や歴史を調査するのは国司の役割である。朝廷が決定していたとはいえ、実務は国司が担っていた。朝廷は国司を通して決定していたのである。ならば、土地を開発した人は国司に減免されるべき事情や歴史や理由を訴えたのだろう。
そうするとやっぱり賄賂の匂いがしますね。
はて。
読んで理解したつもりでブログを書こうとしたのだけれども、
文章にしてみると理解していないことが分かる。
政治って複雑ですね。
もう一度読み直す機会はあるのだろうか。
とりあえず、
奈良平安時代の用語にもう少し慣れていく必要がありますね。
私にとってまだまだ読み応えの本であるということが分かりました。