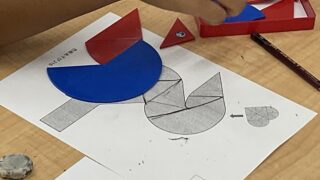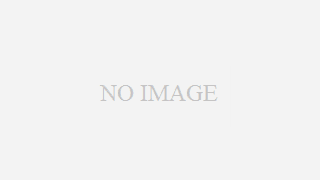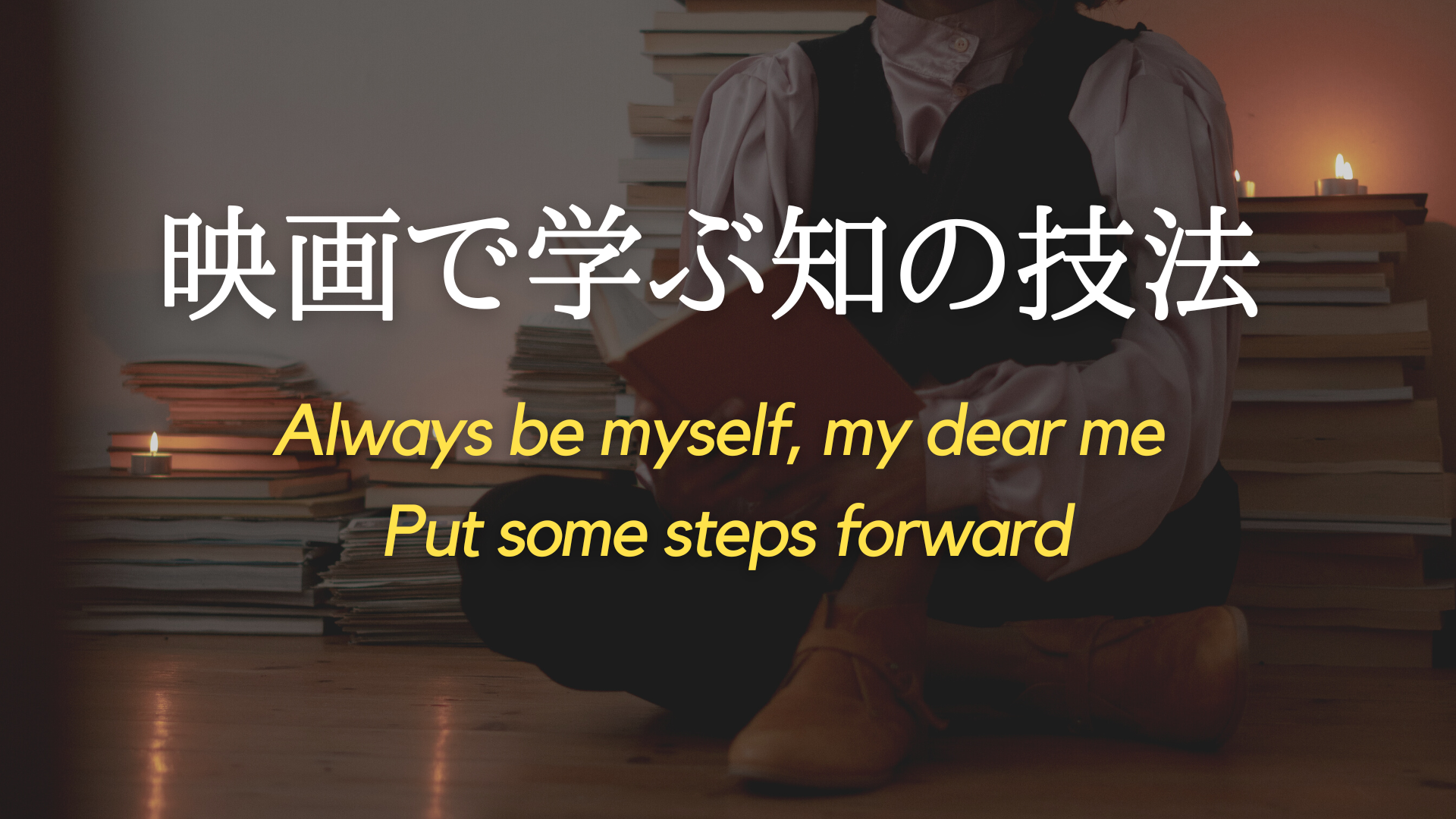「教養は幸運なときには飾りとなるが,不運の中にあっては命綱となる」
by アリストテレス
2024年度予定
次回 7/28(日)【タイタンズを忘れない】
18:30~ 映画視聴
21:00~ Zoom
ネタバレなんて怖くない。
むしろ、何度見ても新しい発見がある。
それが映画。
保守的な田舎町のフットボール・チームをめぐる実話を映画化した感動作。
監督は「フレッシュ」のボアズ・イエーキン。製作は「コヨーテ・アグリー」のジェリー・ブラッカイマー。脚本はグレゴリー・アレン・ハワード。
撮影は「悪魔のくちづけ」のフィリップ・ルースロ。音楽は「60セカンズ」のトレヴァー・ラビン。編集はマイケル・トロニック。衣裳はジュディ・ラスキン・ハウエル。
出演は「ハリケーン」のデンゼル・ワシントン、「60セカンズ」のウィル・パットン、「マーシャル・ロー」のウッド・ハリス、「パッチ・アダムス」のライアン・ハースト、新鋭のキップ・パルデュー、「クルーレス」のドナルド・フェゾンほか。2000年製作/114分/アメリカ
原題:Remember the Titans
配給:ブエナ ビスタ インターナショナル
劇場公開日:2001年4月28日https://eiga.com/movie/51341/
住民同士の対立と不信感によって分断された町がひとつになっていく奇跡を描いた、実話に基づく感動の物語。
タフで強い信念を持つハーマン・ブーン(デンゼル・ワシントン)は、15シーズンの優勝経験を誇り、皆から慕われているビル・ヨースト(ウィル・パットン)に代わって、フットボールチームのコーチに就任する。
2人は勇気と忍耐力をもって互いの違いを理解し合い、いがみ合う選手たちを優勝へ導いていく。
2024年度年間スケジュール
18:30~ 映画
21:00頃~Zoom授業
3月24日(日) 犬神家の一族2006
4月7日(日) レオン
5月12日(日) スクール・オブ・ロック
6月9日(日) 最高の人生の見つけ方
7月28日(日) タイタンズを忘れない
8月11日(日)
9月8日(日)
10月6日(日)
11月3日(日)
12月30日(月) Zoom参加のみ 29日までに感想提出
1月3日(金) .
2月2日(日)
概要 Zoom参加
1週間前までに映画のタイトルをお伝えします。
・アマゾンプライム、TUTAYAなどで映画を見てください。
・なるべく映画を見た直後、専用の用紙に感想文(自由)を書いて提出してください。
アマゾンプライムやそのほかサブスクを使って映画を見れない人は開催日程の18:30にWillbe集合して映画を一緒にいて感想を書きましょう。
自宅からZoom参加もOKです。
感想文提出してくれた子にZoomIDなどを当日お伝えします。
———————-
18:30 集合/映画視聴開始
20:30 感想記入
21:00 授業開始
(授業はZoomで視聴可能)
22:00 解散
過去 扱った映画と予定
1月「ライオン」
3月「グッドウィル・ハンティング」
4月「ヴィンセントが教えてこれたこと」
5月「ギフテッド」
6月「風立ちぬ」
7月「マンマミーア」
8月「最強の2人」
9月「スタンド・バイ・ミー」
10月「プラダを着た悪魔」
11月「ラブ・アクチュアリー」
12月「Always 3丁目の夕日」
1月「天使にラブソングを」 .
2月 「トゥルーマン・ショー」
7月「ライフイズビューティフル」
8月「ショーシャンクの空に」
「はじまりの歌」
9月「きっとうまくいく」
12月「シザーハンズ」
将来の夢。
今知っている「小さな小さな世界」から選ばざるを得ない。
故に、世界を知れば知るほど、夢が変わって当たり前なのです。
だから、「今やりたいこと」が10年後のやりたいことと同じであることは多くない。
広い世界をどんどん知って欲しい。
赤穂が狭いんだと言いたいんじゃない。
赤穂も広いと感じるためにも
いろんなことに触れて欲しい。
いろんなことに触れるには、中学生/高校生は忙しすぎる。
「将来の夢」という言い方は適切ではなく「社会とどう関わるのかを決める」が適切な言い方だと思う。
社会との関わり方を決めれば「職業」は大事でもない気がする。
もちろん、職業が将来の夢であってもよい。
↓↓そんな想いのWillbe図書館↓↓
↑↑Willbe図書館↑↑
映画で学ぶ知の技法
映画を見ることも、様々な文化や人を知るきっかけとなる。
映画をみることも、「世界」を知るきっかけとなる。
世界は必ずしもグローバルを意味しない。
「映画で学ぶ知の技法」は、映画を楽しむだけではなく、その文化的背景や人間分析を行う授業です。
勉強する意味だとか、
頑張る価値だとか、
そんなものは大人のお説教で得るものではなく、自ら感じに行くもの。
この世の中の全てが先生となる。
今回の先生が映画というだけ。
興味関心??
自分に何が向いてる、自分の興味って何?
狭い世界の中で考えるなんて不毛。
確かに、知れば知るほど迷うけれど、知れば知るほど自分の中の1本の線が見えてくる。
それは勉強だけでは見えない世界(だと思ってる。)
そんなわけで、
「映画で学ぶ知の技法」
眠たければ寝れば良い。
対象は、弊塾塾生および保護者様。
進学個別指導塾Willbeが赤穂の皆様にお届けする「映画で学ぶ知の技法」
まずは感じにおいでよ!
先生とは何か?
身の回りのすべてのモノが先生です。
先生が「そこ」に存在しているわけではありません。
あなたが「モヤモヤ」としている時に先生が存在するのです。
あなたがモヤモヤとしたものを言葉にしようとして、はじめて先生が存在します。
だから、
心の中に「もやもや」ってしたものを感じて帰ってほしいんですよね。
もやもやっとしたものを解放してあげるのが
(正しいものを教えるということではなく)
大人の役目なんだろうと思うのですが、、、、
オモロイと思う子にはとことん「もやもや」っとしたものを感じてほしいんです。
勉強に価値があるとするならば「もやもや」っとしたものを言葉にしたりすることなんだと思ってます。
確かに、所謂「勉強」でもそういうものは感じることが出来るのですが、、、、
「あ。。。なんか勉強っておもろい」って思ったときに「もやもや」を感じることが出来れば最高じゃないですか???
「もやもや」を持たずに勉強しても良いのですが、
やはり小中のころに「もやもや」を持ってますと「大学」の価値が倍増すると思うのです。
大学へ行き「もやもや」に出会っても良いのですが、、、
文系不要論なんてあったりしますが、文系も理系も元来「教養」などというものは無駄なものであります。確かに「理系の技術」の「使い方」「価値づけ」「目的」を文系が行う。技術の革新が不幸を招く、だから、文系が「哲学」するなんて言い方もできちゃいますが、、、
何か「もやっ」としたときに勉強への興味が爆発してくるんですよね。
社会と学問がつながる瞬間。
「えーから覚えろといわれたこと」がつながる瞬間。
「えーから覚えろと言われたこと」をすでに知っている瞬間。
それが社会と学問がつながる瞬間。
具体と抽象が一致する瞬間。
だから、、、
子どもたちには、、、、
いまは「え~から学べ!!」とか言いいます。
(「だったらオモロイ授業しろ」なんて反論も聞こえてきそう。)
「知」は強制されるものではない。
だから強制はしない。
テスト勉強はちょっと強制します笑。
講師は私ではありませんが笑
映画の授業には、模範解答があるわけではありません。
あなたの心を解放した感想文を書いてくれればそれでよいと思います。本当に素直に感じたことを書いてください。
その感想から授業内容がきまります。
もやもやっとしたもの、あるいは素直な感想から、「こういう見方もあるよ」って提案してみます。
「正しい答え」を提示したいのではありません。
「映画はこういう風に見なければならない」なんてことを言いたいのではありません。
映画の解像度をあげるというか、ストーリーを追いかける以上の面白さとか、あなた達の思考を一歩先に進めてみたいと思うのです。
(授業するのは私ではありません笑)
2023 生徒の感想抜粋
トゥルーマン・ショー
~略~
番組を作ったクリストフは、トゥルーマンのことをまるで我が子を見るように語っていたが、そうだとしても過保護すぎるように思いました。(トゥルーマンのことを)ヒーローと言っていたが、それは「誰に対しての」ヒーローなのだろうか。クリストフから見るヒーローであってトルゥーマンにその自覚はないし、テレビを見ている人がどう思っているのかは分からなかった。
この世界は、人々が楽しそうにテレビを見ていたから、きっとみんなの理想だったんだと思う。だから、(人権侵害とも思える)この番組自体は否定できない。
もし自分がトゥルーマンだったとしたら、精神が壊れて自〇していたと思います。この物語を作った人の心が心配になりました。
今、自分はトゥルーマンを映画の主人公としてしか見れないが、番組制作者の思惑な気がして少し悔しいです。結局いま自分が「トゥルーマン凄い」と思っているのもトゥルーマンが他人だからであり、物語の主人公だからにすぎない。主人公に本当の意味で同情するのは難しいと感じた。最後のシーンで警官が次の番組を探しているシーンで痛烈にそれを感じた。
現実社会においても嘘より真実の方が恐ろしい気がします。嘘やフィクションに囲まれている今が幸せなんだと思った。真実は自分自身が体験するしかないのだけれど、こんなテーマをフィクション映画で描いているのは皮肉な気がしました。
トゥルーマン・ショーと私たちの人生は全く同じだと思った。私たちは何も自分1人で判断をしているわけではない。この映画は、これまで築き上げられてきた(文化/常識/概念など)全てに逆らい判断して生きろっというメッセージのような気がした。
プラダを着た悪魔
「勝組人生」って結構残酷だなとおもいました。誰もがお金とか地位とか欲しいと思うと思うのですが、そのために「最愛の人」「友人」「努力している同僚」を失うというところが残酷だと思いました。
ミランダについて行くことや地位や大金を手に入れることが幸せではないと思うのですが、本当の幸せは何なんでしょうか?
少なくとも「自分の夢」をかなえることが幸せかもしれませんが、犠牲にする覚悟。。。
———————–
「悔いが残らない方を自分で選べ」という言葉は、どちらかを選び、どちらかを犠牲にするということで、とても大変で、本当に正しい判断化は自分自身でも分からないので、どう判断して楽しく生活していけるのか分からなくなりました。
————————
「プラダを着た悪魔」はミランダの事ではなく、雑誌の読者やマスコミなのではないかと思いました。「主人公が仕方なかった」というセリフを度々言っており、決断の難しさや後悔しないなんて無理だといういうことを物語っていると思いました。
———————-
私が努力できるということはすごくありがたいことだと思った。自分がやりたいことや受験の時、家族や他の人にたくさん努力が出来る環境を作ってもらっていたんだと思い、より一層やる気が出た。
何かに取り組もうとする時、まずは頑張る事が大事だけど、周囲との関係が問題になる。例えばマラソンで一緒に走ろうとして頑張るけど”友人を置いて行かないといけない時”があるのではないかと思った。その辺は気を付けようと思った。
————–
目的を明確に持って、そのために必死になれることがとてもありがたいことなんだと思った。
————–
風たちぬ
二郎にとって飛行機は「夢」であってとても大切なモノだというのが、二郎の夢の中の様子から伝わってきた。
しかし、ファンタジーや輝いた世界ばかりではなく「夢でもあり呪いでもある」と二郎が言っていたように、夢の中の様子も少しづつ変化していたように思う。
大好きな飛行機が戦争に使われ、仲間は誰も帰ってこなないという現実を二郎はどう思ったのだろうか?
最後のシーンを見る限り、
「生きる」と決断したことは分かった。
悲しいシーンなようで生きる決意が表れているシーンだと思った。
———————–
表面だけをみると美しいシーンばかりでしたが、
悲しいシーン、けなげな部分、どうしようも出来ない深い部分などがつまっていて、具体的に頭に浮かんできてこれからの自分に大切なヒントをくれた気がする。
知識って大事だなと思った。
ものすごく奇麗な映画だと思った。
2022 夏 「映画で学ぶ知の技法」 生徒の感想抜粋
「始まる前は怖かった。名指しで意見を求められたらどうしよう、自習室なのに!と思っていた。
でも、講義はとても興味深く飽きずにずっと聴けそうだった。学校だと授業は興味が持てず聴いていられないのに!どんどん話してほしいと思った。
これは差別だ、差別は悪い、とその状況で本当に言えるのかという視点は全く持てていなかったことに気がついた。
竹山先生の前情報(簡単な映画の紹介)でステレオタイプに嵌っていたと思う。笑」
「自分で見た時の受け取り方と解説が結構違っていて、そういう見方もあるのか、と感じた。
自分の中では、幼い子に現実を知らせないように父が苦労する、優しさの物語と受け取っていた。成長した息子には少し 騙された感 があるのでは??それでも『人生は美しい』なんだから、すごいと思う。
色んな人物の異なった価値観が含まれていたと思う。それが良い映画ってことなのかも?」
今回の映画は、僕が普段見る映画とは少し種類が違ったけど、ここまで深く関係などを映画で考え直すことはあまり無かったので、新鮮で楽しかったです。
あと、音楽が好きなのかといわれると、確かにめっちゃ好きなんですけど、多分それは歌が小説と通じるものがあるからだと思います。
グレタと同じような生き方をしている人物が読んだ小説にいた気がするので、読み直して探してみます、ありがとうございました。
また、お願い致します
主人公(良い人)も完璧じゃないんだ。
いままで、創作物の主役をカッコいいと感じたら、そのままその人になりたいと思っていた。今回ならランチョーの頭の良さにばかり気が向いていて、それ以外のところには目が向いていなかった。
他人評価が必ずしも悪いわけではなく、考え方の問題だと気がついた。行き過ぎは良くない。学長が子どもの夢を決めつけていたのも他人評価に基づいて幸せを思えばこそ。それが分かると学長も悪人ではない。
振り返ると、定期テストなど他人評価を気にしていたことが分かった。恋愛の話で言うと、ランチョーは思わせぶり。よく分からない態度。その場で都合よく発言している。見ているときは意識していなかった…。
他の人の感想が聴けるのが楽しかった。同じ映画を観て同じ紙に書いているのに、目の付け所が違ってくることを面白く感じた。
ランチョーは前半と後半でなんか違うな、と思っていたが、授業を聴いてスッキリした。
親の良かれと思う気持ち・学長の想いにも気がつけた。学長の娘は、基本的に父が好きで、親の想いに気がついているからこそ苦しいのでは?ショーシャンクでも、最初から「主人公は無実」としか考えていなかったし、第一印象のままズルズルと行ってしまうところが自分にはあると思う。
インド仏教の話など、自分では辿り着けない視点を持てた。佐々井秀嶺さんは超おじいちゃんだった。(ランチョーの恋愛について)
私は鈍感なタイプかもしれません。ランチョーは自由でいいな、と素直に思っていました。
見ていて疑問に思いまいた。
なんで自分の素晴らしい才能を使おうとしないんだ!!
序盤、頭が悪そうなやつらとからんでいたし、最後、教授とハグしてまっとうに職に就くかと思えば、「女を見極める」だと??
もっと活かせよ。
自分の個性を!
言ってたん!!、友達もそれらしいこと。
「カルフォルニアではなく、シンクタンクに戻れ!!」と思いました。
どうでもいいですが、ただの「屁理屈野郎」から「女を見極めれる」までになって「良い面になったじゃね~か」と思いました。
どんどん自立していくのが普通にいいですね。
(授業を受けてみて)
人に言われたことだけをやり、言われた方向に進むのではなく、自分がやりたいことをやり、自分の方向に行こうと思いました。
といっても、、、、
「将来、何がしたいの?」とか聞かれても答えられないんですけど。。。。
——————————————-
私は、この映画を見て、この主人公は、いい人にで巡り合って、これからいい人生になりそうだな~となんとなく思いました。
ウィルとベンチで2人で話している内容は、自分のことを人に語るときも、相手の事を知るときも大切なことだと思います。
本で読んだことをそのっま話すことは、誰でもできることだけど、それを自分の言葉というか、自分の話したいことを話すのは、意外と難しいかもしれません。
絵をウィルが何も知らずに見たときと、ベンチで聞いた話、その人の話を聞いた後では、たぶん、思うことが変わっていると思います。
もう1つ、私は、驚いたというか、私の思い通りというか、そんなところがありました。
それは他でもないラストシーンです。このまま教授が言っていたように働くのかなと思いつつ、あの女の人のところに「行かないかな~」「行ったら面白いのにな~」と思っていたら案の定行きましたね。
映画が進むとともに、主人公の顔がだんだん真剣になっていくのが、なんとなくわかりました。話していくうちに、自分のつらいところ、認めたくないところを、知る、自覚していく中で、自分にも思うことを言ってくれる友達や他人んがいたことに気づき明らかに変わったように思います。(何なのかは分からなかった)
でも、最後は、すごくよかったです。友達のくれた車をとばして、向かうところがすごく、すがすがしく感じました。