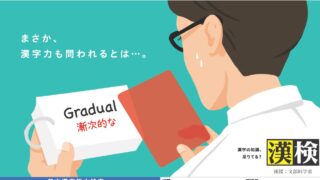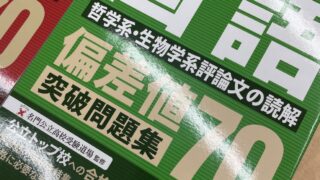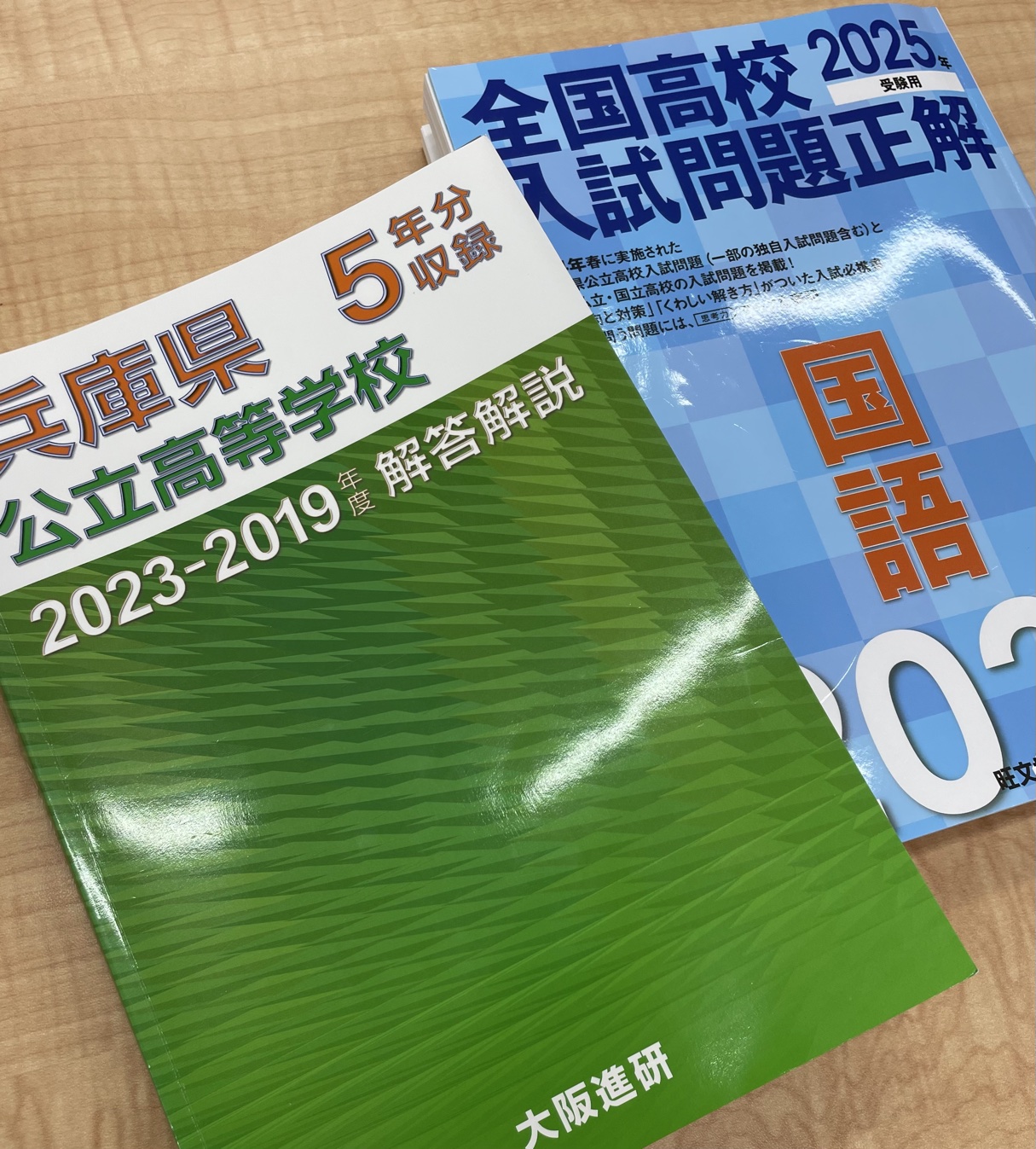兵庫県公立高校入試【国語解説2022】
大問1 新傾向「知ってるつもり」(西村克彦)
私たちは生まれたときから「いろいろなもの」に取り囲まれているが、「いろいろなもの」があるために「考える」ということをしなくなる。
しかし、
「いろいろなもの」の中にも共通していることがあることをしれば、それが「何のためにあるのか?」といったことが考えられるようになる。
「共通性」を知れば、個別特性の意味が明確になる。
問1 漢字の成り立ち知識問題 正解「イ」
ア)象形文字
・物の形を描いた絵から出来た漢字。例えば「魚、山、日、月、水、木、鳥、馬、人、雨、目」など
イ)形声文字
・「意味を表す文字」と「音を表す文字」を組み合わせて新しい意味を表した漢字。例えば「枝、銅、固、注、住、河、校、問、布」など。漢字の9割が形声文字。
ウ)指事文字
・絵や形では表せない抽象的な(実際には目にすることの出来ない)物事を点や線を用いて指示した漢字。例えば「一、二、三、八、本、末、天」など
エ)会意文字
・2つ以上の漢字を組み合わせて1つの漢字に新しい意味を表した漢字。例えば「男、森、明、鳴、位、信、炎、林、考」など
(少しマニアックなので覚える優先順位は低いです。)
「会意文字」と「形声文字」を見分けるのはかなり難しく、辞書によって判断が分かれる文字もある。重要なことは音が関係あるかないかということです。部分の音が全体の意味に関係しているかどうかで見分けていきます。
①同じ漢字の繰り返しの場合は、「会意文字」である可能性が高い(森、炎)
②漢字の9割が形声文字であることから、例外として「少ない会意文字」を覚えておくこと。
③音読みしたときに、同じ「音読み」があるのが「形成文字」
・枝「し」=「木」+「枝(し)」
・銅「どう」=「金」+「同(どう)」
・固「こ」=「口」+「古(こ)」
問2 記号問題(知識問題?) 正解「イ」
「住、柱、注、駐」には「とどまって動かない」という共通性があると答えさせたい問題。生徒同士の会話文に注目して「漢字の成り立ち」から共通性を見出していく必要があるように思われるが、漢字の成り立ちを知らなければ、それぞれの漢字を使ってどれだけ熟語や言葉を想像できるかが勝負。
数学のベン図のような発想。
「住」
・「にんべん」は、人に関係することを意味する。
・「主(ぬし)」は、「所有者」「動作の主体」「集団を支配する人」などの意味を持つ。
↓
この段階では選択肢は絞り切れないが「ウ」は、排除したい。
「柱」
・「木」は、気に関すること
・「はしら」と読む。
↓
この段階でも選択肢は絞り切れない。
「柱」から「エ」が排除される可能性はある程度。
「注」
・「さんずい」は水・河川などに関する漢字。
・「注」を「そそぐ」「注目/注意の注」で読むのか。
↓この段階でも選択肢は絞り切れない。
「駐」
・「駐」は「とどまる」「とどめる」と読む
↓
本文に「『駐』は『馬』を乗り物だと考えればうまく説明できるね」とある通り、「駐」が決定打となる。
「駐」を「とどめる」と読むならば、共通点は、「注」は「そそぐ」ではなく「注目/注意の注」であり、「柱」も選択肢「エ)たくさん集まっている、ア)中心的な存在」が排除され、「イ)とどまって動かない」が正解となる。
問3 知識問題 正解「水」
問2が正解できたうえで、本文中にある、以下の2文の対比。
・「注」は「そそぐ」という行為の結果として「③」が「とどまって動かない」のだと考えられるし、
・「駐」は「馬」を乗り物だと考えればうまく説明できる。
「さんずい」が水に関する意味をあらわすと知っていれば正解できる。
問4 記号問題 正解「エ」
課題本文の要約と対比
・「(自分で作っていないし/共通性を知らないから)『いろいろある』というのは、人をそこで立ち止ませる。」
しかし
・「共通性を知れば「いろいろ」が何のためかと考えるようになる。」
よって、「立ち止まる」は「考えない」の言い換えだと考えられる。
ア)「諦める」が違う。そもそも考えようとしていない。
イ)「使用をやめさせる」が違う。まったく違うと言って欲しい。
ウ)「人の関心を製品の特徴にむけさせる」が違う。
→いろいろなものがあるから考えない。
→だからこそ共通性について考えたい
→共通性にきがつけば「製品の特徴」に気が付く
↑課題文の「人をそこで立ち止まらせる」と書かれている時点では「製品の特徴」の話はしていない。
問5 記号問題 思考力なのか?知識問題なのか? 正解「ア」
学校の教室の椅子、理科室、図工室の椅子をくらべて「共通性」と「個別特性」について考える問題。
絵があるとはいえ、リアルに実験室の椅子をイメージできますか笑??
学校の椅子が「快適性」を実現していることに納得できる笑??
まずは、さらっと考えて絞りやすそうなものから絞っていく。
↓
⑦のソファーについて考えて、ソファーが「快適性」「安全性」なのかを考えていくと「安全性」よりも「快適性」の特性を持っていると考えたい。(いったん)
↓
⑥「実験室の椅子」が「収納性」「動かしやすさ」なのか「収納性」「耐久性」なのか。。。。
よくわからん笑
↓
⑤「教室の椅子」が「快適性」「耐久性」なのか「快適性」「動かしやすさ」なのか。。。。
よくわからん笑
↑と考えた人はアカンです。
問題文に「【会話文】をふまえて」と書いてありますからね!!
会話文を見てみると、
「実験質の椅子は、~収まらないと~~邪魔になる」
「教室の椅子は、~座り心地のよさがないとね~移動させて使うことも多いよ」
と書かれてあるので、
「ア」
・⑤快適性と動かしやすさ
・⑥収納性と動かしやすさ
・⑦快適性
が正解になる。
間違えた人は、「会話文」に書いている内容を要約する練習が必要かもしれないね。
問6 書き抜き問題
問題文を読むと、課題文の中から「何を意識すれば、何に気が付くことが出来るから、より良い使い方がが分かる(出来る)」を抜き出せばよいことが分かる。
本文の文脈から考えると「共通性を意識すれば、個別特性に気が付くから、よりよい使い方が出来る」の言い換えを探していきたい。
⑧「共通性が貫徹していること」
⑨「用途に応じた工夫」
大問2 漢文「世説新語」(劉義慶)
問1 書き下し文から漢字を1字抜き出す問題 正解「虎」
「これを見る」の「これ」
指示語は、基本的には(例外もあり)、前に指示内容がある。
漢字1文字なので「虎を見る」と考えたい。
指示語の例外。
→基本的には、指示語の直前ではあるが、かなり前のこともある。
→「実際は、そうでもないのに、ひどく高い点数をとったと思い込む」の場合は、「高い点数」が指示内容になる。
問2 返り点をつける
兵庫県公立高校入試国語頻出なので必ず出来るように練習しましょう。
書き下し文と見比べて漢字に番号をつけてみましょう。
そうすると、
①
②
⑧
⑦
③
④
⑤
⑥
の順番になっていることが分かる。
⑦⑧を入れ替えるのが「ㇾ点」
→⑦⑧の間に「レ点」
⑦⑧をセットにして後から富ませるのが、「一二点」
→⑥から⑦にいくので、⑥の下に「一」、⑦の下に「二」
問3 主語を考える問題 正解「a:ア」「b:イ」
ここを間違える人は、普段から主語と述語に対する意識が低いと言わざるを得ません。主語と述語を補うドリルも少ないため、古文や漢文を読むときは「主語」「述語」を把握するようにしましょう。
そもそも「(英語とくらべて)日本語は主語を省略していることが多い」さらに「現代文より古文の方が主語を省略している」のです。
しかし、「述語が省略されていることは(ほぼ)ありません」
普段から「述語」に対する「主語」を「誰が?」「何が?」と自分で補っていきましょう。
それが出来ないということは、文章を読めないということです。
問4 記号問題 正解「イ」
ア)積極的に行動できないが違う。積極的に行動できない王戎ならば虎の前にいくわけがない。
イ)正解
ウ)虎の前に行くことは一見「無鉄砲」「後先考えずに行動すること」に思えるかもしれないが、本文にそのようなことは書かれていない。かつ、ウ)を選んだ人は、おそらく「爪と牙を切り取った虎」という部分を読み飛ばしているのかもしれない。
エ)「人の意見に流されない」が違う。本文中に、誰かが王戎にアドバイスしたというような記述は一切ない。
ーーーーーーーーーーーーー
大問3 古文「徒然草」(兼好法師)
問1 現代仮名遣い
歴史的仮名遣いの「はひふへほ」は、現代仮名遣いで「わいうえお」と書きます。
例)
・あはれ → あわれ
・かひなし(甲斐無し)→ かいなし
・たまふ(給ふ・賜ふ)→ たまう
・うへ(上)→ うえ
・なほ(尚・猶)→ なお
例外①「助詞」
・このこと「を」
・赤穂「へ」帰るに
・今「は」
例外②「語頭」
・はた言うべきに
・ひぐらし
・ふと
・へいぜい
・ほい
問2 「わづらい」の意味 記号 正解「ウ」
暗記ではなく、文章の流れから意味を推測する。
・蹴鞠の予定があった。
↓
・雨がふった。
↓
・庭が乾いていない。
↓
・「おかくず」を庭にまいた。
↓
「わづらい」がなくなった。
流れを把握できれば「損失」「病気」「不足」が誤りだとわかる。
問3 記号問題 正解「イ」
ア)「砂ではなくおかくずで対応した」が違う。
ア)を消し切れなかった人は、後半の吉田中納言のセリフを読み間違えています。「乾いた砂を用意していなかったのか」と聞かれて、恥ずかしくなっているので、本来は「乾いた砂」を用意しておいた方が良かったことが分かる。
イ)正解
ウ)「車を準備してた入道の気配り」が違う。車を誰が用意していたのかは書かれていない。
エ)「乾いた砂」が違う。
問4 記号問題 正解「エ」
ア)「おがくず」を使った方がよかったという話なら正解。しかし、問3ア)と同様の理由で間違い。
イ)「ものを教わる」が違う。誰かに教えてもらったような記述はない。
ウ)「だまされる」が違う。
エ)正解
大問4 小説「櫓太鼓がきこえる」(鈴村ふみ)
本文要約
・門限を破った篤が師匠に呼び出され、予想通り怒られる。
↓
・篤が謝ると師匠が「心技体」の文字を見せながら「心」の重要性を説く。
↓
・引退した師匠の目は、現役時代同様に強い光があった。
↓
・師匠の部屋を出て一階に降り「呼び出し」の練習をする篤。そこに先輩力士の坂口さんが差し入れをもってきた。
↓
・坂口さんが「やる気をだしたのに、失敗して、怒られて、嫌にならないのか?」と篤に聞いたところ「失敗したからこそやらなければいけない」と篤が答える。
↓
・「失敗しても誰かが助けてくれた。だから、次こそ失敗してはいけない」と篤は思っている。
↓
坂口さんも「篤が頑張っているから、俺も頑張る」という。さらに、「プライドを捨てて弟弟子である武藤も練習にさそう」とまでいう。
↓
篤は、弟弟子を練習に誘うと決めた坂口さんの葛藤を想像する。
↓
そこから篤は何度も呼び出しの練習をした。
問1 漢字の読み
②)「座敷(ざしき)」
④)「途端(とたん)」
⑤)「絞られる(しぼられる)」
問2 品詞が異なるものを1つ選ぶ 正解「エ」
ア)「いつぞや」 動詞を修飾しているので副詞。
イ)「きっと」 動詞を修飾しているので副詞。
ウ)「さすがに」形容詞を修飾しているので副詞。
エ)「ほのかな」名詞を修飾している形容詞に見えるが、活用して「ほのかだ」で言い切るので形容動詞。
問3 傍線部の意味を選ぶ ①「エ」 ⑧「ア」
知識問題。
言葉の意味を辞書で確認しておきましょう。
問4 記号問題 正解「ウ」
「ア」か「ウ」かで迷いたい。
ア)
大問5 評論「計算する生命」(森田真生)
本文要約
テーマとしては難しいテーマですが、兵庫県らしくて良いですね。森田さんがおっしゃる「生命の持つ自律的なシステム」について考えてみましょう。兵庫県に限らず大学入試/高校入試において「哲学」「生物」関連問題は頻出です。学校のテストや模試において「哲学」「生物」分野の問題が出れば、内容を掘り下げるような意識をしておいても良いでしょう。
「計算とは何か」という問いを通して、人間の思考と生命の本質を探る内容です。
囲碁や将棋でAIが人間を打ち負かすようになるなど、森田さんは、近代以降の数学やコンピュータ科学における「計算機」(電卓⇒パソコン⇒AIなど)の発展を振り返りながら、それがいかにして人間の営みから切り離され、機械的・効率的な処理へと変化してきたかを述べています。「計算」(AIなど)はまだ人間らしくないのです。つまり、「自分で計算してくれる便利な機械」の域からは脱していないのです。まだAIは「自律的に何かを行ってくれる」わけではなく、人間の活動の一部を「自動的に」行ってくれるだけなのです。現代科学と言えど「(ドラえもんのような)自律的に何かを行う」機械を生み出していません。
一方で、森田さんは「計算」を単なる手続きや処理ではなく、生命活動の一部、すなわち世界と関わりながら意味をつむいでいく営みとして捉え直します。たとえば、言葉を話すこと、歩くこと、誰かと関係を築くこともまた「計算」であり、そこには身体性や関係性が不可欠です。
生命の自律性は、外界からの刺激に単純に反応して行動に移しているわけではなく、外の出来事を正確に写しているのではなく、自分の中で「こうなったらこう動く」といった反応を何度もくり返しながら、自分自身を保っている仕組み(システム)と言えます。つまり、「Aだったら必ずBである」と決まっているのではなく、AだとしてもBで良い時があって今はBなのかもしれないといったものが脳内にあるかないかです。
では、生命そのものであるかのような「自律的なシステム」を人工的に作り出すことは可能なのだろうか。この問いに関してはまだ誰も分かりません。
森田さんは、AIやアルゴリズムが進化する現代においてこそ、人間の持つ非効率で不確実な「計算=生きること」の価値を見つめ直す必要があると訴える。つまり、「ドラえもんのような世界?」を急ぎ過ぎるあまり、「私達人間」が「自動的な機械」になる可能性もあるのです。それでは本末転倒です。あくまで私たちは「機械に自律性をもたせる」ということが目的なのです。
単なる手続きや処理ではない生命活動の一部としての「計算」とまざりあう姿勢が必要です。
(確かに、AIと言われているものの中には、条件分岐(AだったらBだと答える)と決まっているものが多いようにも思います。それが人間だったら嫌ですね笑 )
(ChatGPTの登場で、「内なる反復」を機械が行っているようにも私には見えるのですが、どうなのでしょう?? Botのように条件に反射して答えているだけなのでしょうか??)
問1 漢字
漢字の学習は、○暗記ではなく「漢字そのものの意味」を知り、「なぜその熟語に、その漢字が使われているのか?」を意識していけば、覚える量が減ります。
A 正解 ウ
B 正解 イ
C 正解 ウ
問2 文/文節(文法)
正解「発想」
傍線部は「分かつ」
主語と述語の整理
述語・・・根ざしていた。
主語・・・(こうした)発想
主語と述語を整理したうえで、「分かつ」がどの言葉に繋がっている(修飾している)のか考えてみて欲しい。
「分かつ発想」となる。
文法知識
「わかつ」は「五段活用の動詞/連体形」であるから体言(名詞など)を修飾している。
未然形の語尾が「ア段音」になるのが5段活用の動詞。
ただ「分かつ」を使用したことがない中学生には、
「分かたない」
「分かちあう」
「分かつ」
「分かつ時」
「分かて」
と活用するのは難しいかもしれない。
問3 文脈理解
正解 ウ
前後の内容を整理すると、
生命と計算の間には距離がある。
↓
最先端の技術(計算)も「①」「自動的」な機械の域を出ていない。
↓
今のところ人間は、行為する動機を自ら生み出せるような「自律的」なシステムを構築する方法を知らない。
となる。
「自律」と「自動」の対比を行っている文章において、設問では、~~~という「自動的」な機械というように、自動的の意味を答えれば良い。
「自律」と「自律」の違いについて、分かりにくければ本文12行目読み進めていただければわかるだろう。「外部からの入力(刺激)⇒反射的に動く生物」など書かれてあるが、これは「自動」のことを言っているが、そこから筆者は、生命の活動は「外部からの入力(刺激)⇒反射的に動く生物」ではないと説明している。
ア:内部で生み出した。 ×
「行為する動機を自ら生み出せる」のは「自律」である。
イ:外部から与えられた 〇
ウ:他者に与える ×
まったく関係ない。
エ:自力で見つけ出す。×
自力で見つけ出すのは「自律」である。
問4 生命が「自律」的に動くというのは、分かり切ったことでもない。
傍線部以降に、生命が自律的に動くということが(私たちにとって)当たり前の話になった歴史が書かれている。問3ともつながるが、それは認知科学が「生物の認知システムを計算機同様、他律的な支配に作動する」ものだと思っていたからで、単純な「反射」が否定され始めたのはおそらく1900年代後半の頃です。
設問は、何故「生命が自律的だ」ということが常識ではないのか?という問い
ア) 〇正解
イ) × 本文に書かれてはいるが、設問と関係ない。
ウ)× 「見出すのが困難だから」が間違い。
「限界を指摘し」という言葉を「困難」と変換して選んだ中学生もいるように思うが、「特殊な点」に限界があったというだけで、「生命の本質を自律性に見出すのが困難」なわけではない。
エ)×
一見正しそうに見えるので、迷うとすればア)エ)で迷って欲しい。だが、本文を読めているならアの方が正確に書かれてあるし、生物の認知システムを「外界からの刺激に応じて作動する」と断言している箇所もなければ、事実だと述べている箇所も本文にはない。
問5
分かりにくく少しややこしいで直前までの文章を「例えば」「ところが」に注目して、整理して出来ていれば大丈夫だろう。
傍線部の「認知主体」とは「カエル」のことです。「認知主体の外から」と書いてあるように、「例えば」直後の「第3者目線」「外からの観察者」と混同しないように設問選択肢を読みたい。
ア) ×
「自分の世界の外側の存在」が違う。カエルにしてみれば「カエルの世界」しかないのである。
イ) ×
「外界のハエにただ機械的に反応している」が違う。カエルの世界からすれば入力も出力もないのだ。
ウ) ×
多少迷っても良いかもしれないが「外界に存在するハエを認識して」が違う。カエルにしてみれば「カエルの世界」しかないので、内も外もない。
エ) 〇 正解
問6
マトゥラーなの研究内容を丁寧に読んでおく。点線で囲まれた文章のどの言葉が本文のどこの言葉の言い換えなのかを意識できていればよい。
a)については、やはり述語⇒主語⇒目的語の順番で整理したい。
述語 「確かめようとした」
主語 「マラトゥーナ」
目的語「何を??」
神経系に(a)からの刺激に対応する活動パターンがあることを
☝この時点で(a)に入る言葉を「自分の言葉」で思いついておく必要があります。そうでなければ「本文」を読めているとはいいがたいです。「外界からの刺激」などいろいろ迷う言葉はあるが8文字なので「客観的な色彩世界」が正解である。
b)についても、述語⇒主語⇒目的語の順番で設問を整理したい。
述語 (b)ではないか
主語 生物は
「自律的なシステムを持っている」「自己自身に反復的に応答し続けている」といったマラトゥーナの結論を選べばよい。
ア) ×
「外界を内的に再現している」が違う。
「外界を再現しようとしているのではなく」「外界を内的に描写しているのではなく」と本文には書かれている。ア)を選んだものは「外界を内的に描写しているのではなく」を読み飛ばしたのかもしれません。
イ) ×
「周囲の環境とは無関係に」が違う。
「外的な刺激をきっかけとしながら」と書かれてある。
ウ)×
「固定的なパターンの活動」については一切本文に書かれていない。個体ごとの独自のパターンは作るもののそれは固定的ではない。
エ)〇
問7
指示語を明らかにしてから選択肢を吟味していただきたい。
中学生の国語や英語を指導していると「設問として聞かれて初めて指示語を考える」読み方をしている人を良く見ます。しかし、その姿勢では文章を読める子にはなりません。英語において「彼は中学生です」と和訳していて「彼ってだれ?」と聞くと「分かりません」という答えが返ってきます。それではいけないのです。
何が本末転倒なのか?
計算(機械)を人間(生命)に近づけようとしているというより、人間を機械に急速に近づけようとしていることが本末転倒だと言っています。
ア)×
「機械を人間に近づけるという」こと自体は間違ってはいないが、だから本末転倒であることにならない。人間を機械に近づけようとすることが本末転倒なのです。
イ)×
まったく違う。
ウ)〇
エ)×
「混同」という言葉が違う。
明確に「人間を機械に近づけようとしていることが本末転倒だ」と言っている。
問7を外した場合、問4を忘れていることが原因なようにも思う。
つまり、「機械と人間には大きな隔たりがあり、機械には自律的な活動はできない」と筆者が述べてドラえもんの世界のみで問7を考えた場合、エ)を選ぶのかもしれない。
問8 結構難しい。全体正答率7.9%
本文全体の要約が出来ているかどうかを問う問題。
ここについては大学受験生も苦手としており、近年流行している「総合問題」「推薦入試小論文」で問われている部分は、問8を正解できるかどうかと言ったことです。
問7までのように局所的に読めば正解できる問題と違い、本文全体のながれを意識する必要はある。しかし、問1~問7までを丁寧に正解できているならば、問8も正解できる。
そういう意味で兵庫県公立高校国語は良い問題が多い。
ア) 〇
あれだけ壮大なAIの話をしておき、人間が機械に近づくこと(自律ではなく自動)に警鐘をならしている文章であるから、物足りない気がするのは理解できます。しかし、本文の内容には完全一致しています。その点に騙された?人も多いのではないだろうか。しかし、その他の選択肢には矛盾点があるので、ア)を選ぶしかない。納得は出来ないが消去法である笑
イ) ×
「まだ誰も答えをしらない」と書かれているので断言するのはおかしい。
ウ) ×
「ありのままの認知現象を捉えようとするなら」「外部に本当の世界を措定してしまう」と書かれてあるので違う。独立した主体を捨てなければならないのである。
エ) ×
「過去を否定し」が違う。
機械と人間が混ざり合うことが大事だと言っています。