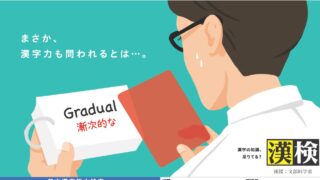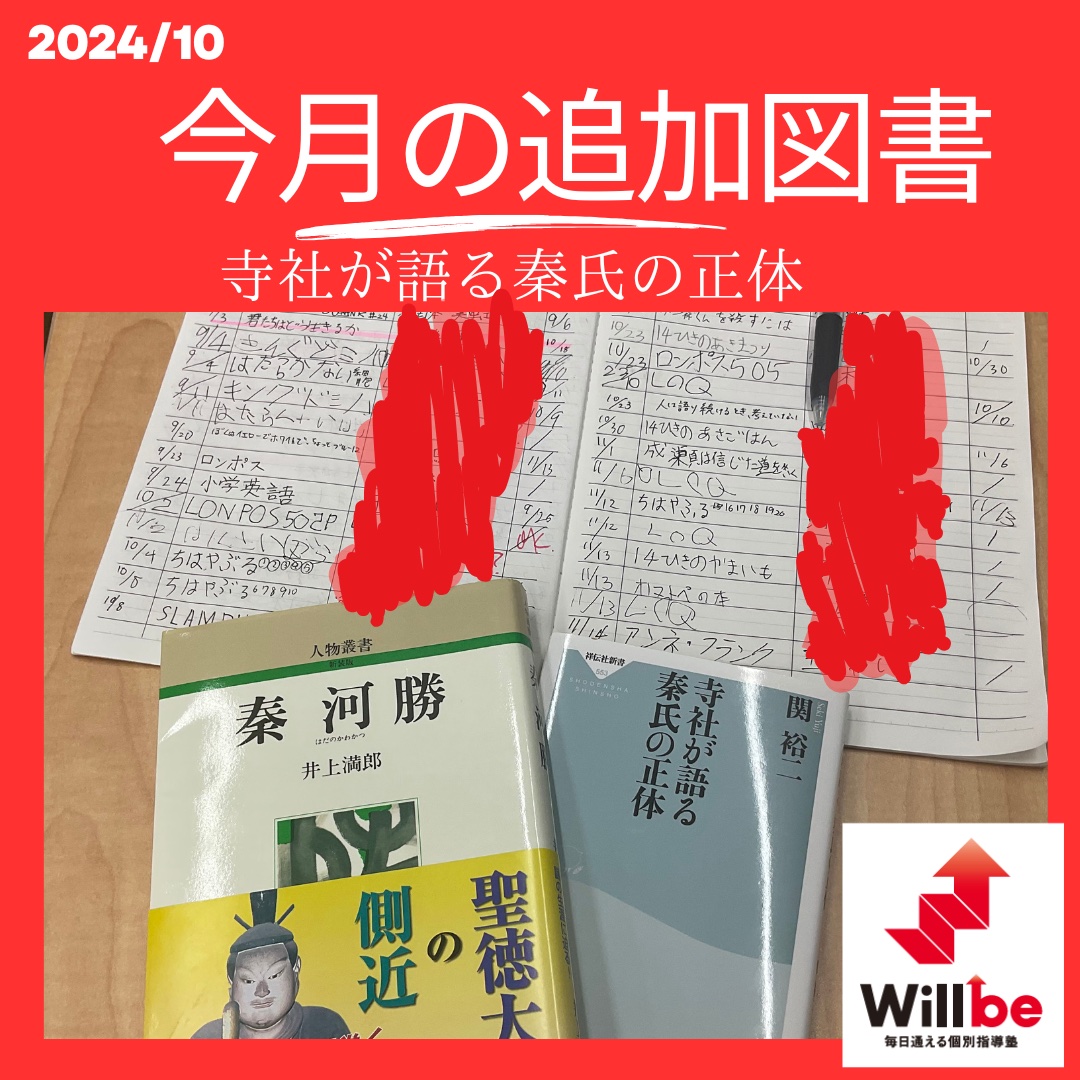今日もブログを読んで下さってありがとうございます。兵庫県赤穂市の個別指導塾Willbeの光庵です。さて、今月もやって参りました。今月のWillbe図書館追加図書。
赤穂市坂越にある大避神社。この神社に祀られている「秦河勝(はたのかわかつ)」という人物をご存じでしょうか?
今回は、関裕二さんの『寺社が語る秦氏の正体』を通して、この謎多き渡来系氏族・秦氏と坂越との関わりについて掘り下げてみました。Willbe図書館より11月の追加図書としてご紹介します。
古代史・神社・渡来人・そして坂越のお祭りに興味がある方にとって、ちょっとディープで面白い内容かもしれません。
『寺社が語る秦氏の正体』を読むきっかけ
Willbe図書館
Willbe図書館の今月の追加図書は、完全に私の趣味です(笑)。生徒のことなんて考えずに趣味に走った11月の追加図書です。
塾生へのお知らせ
あの本を読みたいけれど、学級文庫や赤穂の図書館ではいつもだれかが借りている。そんな本があれば是非教えて下さいませ。
「Willbe図書館」においてもらえるかもしれないよ!
「秦河勝」って誰?基礎情報と私の疑問
獅子舞と私とお祭りと歴史
聖徳太子と秦河勝と私の関係
母親の実家が坂越であったことも影響し赤穂市坂越の船渡御祭りが私は好きでした。かつ、歴史は好きでした。なぜだか分かりませんが、小さいころに見た大河ドラマ「毛利元就」だとか小説「真田太平記」(池波正太郎)「徳川家康」(山岡壮八)「坂の上の雲」(司馬遼太郎)にハマっていた記憶はあります。
小学校や中学校では完全に浮いてました。そりゃ休み時間にそんな本を読んでいたら浮きますよね。
ぶっちゃけ”GLAY”も”ラルク”も”19”も”モーニング娘”もミュージックステーションもHeyHeyHeyも、休み時間の会話について行けないのはあまりにもマズいと思ったので見たり聴いたりしているだけでした。(そういう意味では、今では中学生に「周りと違っていても大丈夫」と伝えられるようになりました。)
小さい頃の疑問は大人になってから解決される。
さて、そんなわけで坂越の大避神社が「秦河勝」を祭神としていることぐらい知っていました。普通は小さいころに出会ったよく分からない知識は年を重ねるにつれて再登場して解決してくれます。少なくとも心のノートにメモされているものは、何かしらのきっかけでどこかで解消されることが多いのです。
毛利元就も真田幸村も司馬遼太郎についても小学生の頃と比べて大分詳しくなっています。
ところが、この「秦河勝」に関しては私がいくら年を重ねても登場してくれなかったんです。「聖徳太子(厩子皇子)に気に入られていた」「渡来人」「日本の文化に影響をもたらした」といったことはなんとなく知っていますが、それぐらいは10代の頃に知っていました。一向に、誰なのだかわかりません。
昔からの疑問「秦河勝って誰?」が再燃したきっかけ
2024年は久しぶりに獅子舞の話題に触れることが多く、私の中の「秦河勝って誰やねん?」問題が再燃しているのです。少しネットで調べてみると「ユダヤ人」などというキーワードが出てきて「どゆこと??」状態であります。
そこでっ!
もう秦河勝と秦一族に詳しくなろうと個人的にWillbe図書館に「寺社が語る秦氏の正体」を追加です。
「寺社が語る秦氏の正体」関裕二/祥伝者新書/2018

坂越の大避神社と「12」という数字の不思議
「秦氏とユダヤ人の関係」について書かれている箇所はまったく私が知らない情報だったので一生懸命読んでみました。
その一説に「梅原猛は」「坂越大避神社が12の数字が重視され、祭礼にも『12』が頻出することについて、これが、キリスト教とつながっていた、ひとつの証拠ではないかと指摘している」(P78)と書かれてありました。
確かにキリスト教やイスラムの世界では「12」という数字を大切にしている気は致します。「12使徒」「12部族」といった言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?エヴァンゲリオンなどいろんな物語でオマージュされています。
オモシロそうなのですが「そう考えても良い根拠はいくつかあるが、よく分からない」という「歴史あるあるな結論」なのは押さえておきたいです。なぜこの件が本書に記載されているのかは謎で仕方ありません。
キングダムや三国志と同じように「物語」「事実」「古い物語」といったものは分けておく必要はありますね。
それはさておき、私にとって重要だったのは「坂越大避神社が12の数字が重視され、祭礼にも『12』が頻出すること」です。知りませんでした。
本書では1行程度の記述だったのでイメージが出来ず少しネットで調べてみますと、赤穂の方がブログを書いてくださっておりました。この方は、確か、坂越の造り酒屋「奥藤酒造」で開催されている「奥藤市」などを運営されている方(のような気が致します。)です。
まず拝殿へ向う階段は12段。
境内の井戸は12本の石柱で作られています。
この神社への初穂料はその昔12銅で、
今も12の倍数が収められているとか。
また神社を守る社家も12家、
祭りの日程も旧暦の9月12日、
その祭りの祭礼船も12隻。
ぜひ見てほしい拝殿の天井絵も、12×8枚あります。
坂越を愛する哲学者、梅原猛さんの石碑を囲む石も12個。これは、河勝が12人の供人を伴っていたことからと伝えられています。
https://www.travel.co.jp/guide/article/5275/
知りませんでした。
次回、大避神社を訪れる時(おそらく桜の季節、大避神社付近にある船岡園の桜もかなりキレイなんですよっ)は、新しい目で大避神社を見ることが出来るかもしれません。
ウキウキです。
仏教でも大切にされている数字「12」
とはいえ、12という数字は仏教でも大事にされている場合もあります。ユダヤと秦氏の関係については、他にも主張や言説の根拠はあるようですが、仮にユダヤ人がシルクロードを通って日本に訪れて、という証拠にはならないでしょう。いまの時点で「だから何なんだ?」という気持ちではあります。
ただ、、、
大避神社のパワースポット感は増しますね笑
日本書紀と秦河勝|「なぜ坂越に?」を歴史から読み解く
通説と教科書的な知識の整理

私は、赤穂市のHPや坂越の船渡御祭りを紹介するHPに、もう少し詳しく書いて欲しいと、少し不満を持っていました。確かに、蘇我入鹿事件が原因だったといったことは書かれております。
つまり、大化の改新、中臣鎌足、蘇我馬子、天智天皇あたりの時代です。中学の教科書的には、公地公民制(豪族が私有していた土地や人民を国家が直接支配する)班田収授法(戸籍を作り、公地を公民に分け与え、死ぬと国に返させる)租・調・庸の税制(公民に税や労役を負担させる)といったことがテストに出題されるあの頃です。
しかし、HPを読んでも釈然としません。
「大化の改新」や蘇我氏、中臣鎌足との関係を整理
大化の改新については、こちらのNHKDVDがおススメです。ただのドラマです笑 秦氏についての知識を深めようとするならば、やはり大化の改新前後の登場人物を一通りは知っておく必要はあるかもしれません。
出演 岡田准一, 渡部篤郎, 木村佳乃, 山口祐一郎, 小栗旬など)
日本書紀には、聖徳太子(厩戸皇子)が秦河勝オシで重宝しており聖徳太子と蘇我氏は仲が悪かったと書かれているそうです。秦河勝は聖徳太子によって「小徳」(”冠位12階”の上から2番目、聖徳太子が推古天皇11年(603年)に制定した日本初の冠位制度)に抜擢されていたそうです。大化の改新前後のお話は兵庫県知事選2024を上回る政治闘争だったり壮大な兄弟喧嘩です。そうすると政治闘争に打ち勝った「蘇我氏」から嫌われている秦河勝が、どこかに逃げなければならなかったというのも納得は致します。
そういえば上記DVDに渡来人が描かれておりましたが、あれは秦氏だったのかな?記憶が薄すぎておぼえておりません。時代的には渡来人はいつだって重要な役割を果たしますから、秦氏もその一部で、有名人は秦河勝ぐらいではあるものの、結構な勢力を誇っていたのでしょう。
関裕二さんの疑問に「歴史に残る敗者の側の視点を学ぶ」
ここまでが一般的なお話で「寺社が語る秦氏の正体」の著者「関裕二」さんによればもっと奥深い仮説があるようです。「日本書紀によって仕組まれた上宮王家(聖徳太子とその子孫)滅亡事件のカラクリ」が重要だそうです。つまり、蘇我氏と秦河勝の仲が悪くて坂越に秦河勝が落ち延びてきたならば、蘇我氏は倒される側であるから、坂越に落ち延び続けたのはおかしいとおっしゃっております。
蘇我氏が中大兄皇子らに倒された後に、秦河勝は中央に戻ることが出来ますよね??
そうかもしれません。基本的に歴史は「勝者の記述」「勝者の権威」「正当性」みたいなもののために書かれていることが多いという前提にたてば、真実は別のところにあると言われると興味を持ってしまいます笑
いうなれば教科書に書かれていない歴史の真実みたいな話です。YouTubeで流行りそうなタイトルですね笑
聖徳太子⇒大化の改新
赤穂市の中学校が採用している教科書には大化の改新周辺の件は『「律令国家」を目指して』という章で以下のように記述されています。
7世紀初め、反乱で滅んだ隋の武将が唐を立て・・・唐の皇帝は律令という法律で国を治め・・・唐は隋と同じく、積極的に周辺諸国に兵を送って高句麗(朝鮮)も攻撃したため、東アジアの緊張はさらに高まりました。
(そのような情勢により)倭国は国家の仕組みを整える必要がありましたが、聖徳太子の死後、蘇我氏が一層力を強め、権力を独占してしまいました。中大兄皇子(天智天皇)は、中臣鎌足(藤原鎌足)らと図り、645年蘇我氏を倒して政治改革に着手しました。・・・この改革を「大化の改新」とよびます。しかし、その改革の実現にはこのあと50年ほどかかりました。
一般に、大化の改新周辺の歴史事情の構図は、新しい国家(改革/律令国家)を目指すにあたり既得権益側の蘇我氏Vs改革派の中臣鎌足/中大兄皇子の政治闘争だったと言われております。
聖徳太子の「17条の憲法」は「和を以て貴しとなす」という言葉が象徴するように「理念」「スローガン」の集合体です。現在の法律/憲法とは少し意味合いが違います。
一方で、律令とは「刑罰や行政法」のことです。17条の憲法の後に「律令」を志す訳ですが、今まで自由を謳歌してきた人たちが、明確な「文章」「刑罰」によって縛られることを嫌うのは感覚的に分かりますよね。自分たちの力で土地やお金を手に入れたにも関わらず奪われるのですから。。。
その辺が大化の改新周辺の混乱です。
関裕二氏の主張と私の学び
関裕二氏の主張
「寺社が語る秦氏の正体」では、
- 中央集権(改革派)賛成派は蘇我氏だったのではないか?
- 中臣鎌足/中大兄皇子こそ権力に魅了された側ではないか?
- 聖徳太子の存在否定
中臣鎌足/中大兄皇子が不都合な真実を隠すために権力闘争において架空のエピソードを盛り込み事実を捻じ曲げなければならなかった。それが聖徳太子一族。 - 蘇我氏と秦氏は仲が良かった。
秦氏は渡来人のなかでも日本に来るのが早い集団で、一定の地盤を築きあげており蘇我氏との関係も良かった。 - しかし、すでに地盤を気付き上げていた秦氏にとって蘇我氏が目指した中央集権を受け入れることは出来なかった。
- 蘇我入鹿を倒したのは、中臣鎌足や中大兄皇子ではなく秦河勝だった。
既得権益側の秦河勝は蘇我入鹿を倒したものの、中臣鎌足や仲大兄皇子が続ける改革にもついて行けず中央に居場所を失った。 - だから坂越に逃れてきた。
と主張されております。
なるほど、分かりやすい。論理だけ見てみると説得力があります。
しかし、私自身は日本書紀など細かい資料までは分かりませんし、時系列を完全に整理できたわけでもないのでこれが事実だというつもりはありませんっ もう少しいろんな本を読んでみたいというのが素直な感想であります。
「秦氏」=「秦一族」??
「氏」という言葉からどうしても秦氏と言われると「血縁関係で結ばれた一族集団」というイメージを持ってしまいます。しかし、この固定概念はどうやら秦河勝って誰やねん?を考えるにあたり邪魔のようです。すこし個人的にすっきり致しました。
「秦氏」は血縁関係を持った一族なのではなく、
3世紀~5世紀ころ、中国や朝鮮の状況が悪く日本へ移住してきた集団を、当時の日本政府?権力者都合によっていくつかの勢力として「秦氏」と読んだという理解がよさそうです。なるほど。
まとめ
マニアックな登場人物が多いですから、この辺の歴史をあまり知らない方は先ほどのDVDを鑑賞してから読まれても良いかもしれません。
「秦氏」とはいったい何者なのかといったテーマで読み進めていきますと、当時の税制度や国家統治の歪や江戸時代や昭和にまで通じる歴史の闇のようなものが繋がってくるとはあらためて歴史の奥深さを感じた私です。
「寺社が語る秦氏の正体」は、「八幡神宮やそのほか神話と秦氏の関係」あるいは「なぜ、能/狂言/雅楽といった伝統芸能と秦氏が結びつくのか?」といった別の疑問にも答えてくれておりました。東儀秀樹さんが坂越の祭りに参加された時、それっぽい有名人っぽい人が来たと嬉しそうに雅楽船を見物していた小さい頃の私にとって、なぜ東儀さんと坂越が所縁が深いのか小さい頃の私には皆目見当もついておりませんでした。それはまたの機会と致します。まさか観阿弥/世阿弥まで登場してくるとも思いませんでした。
しかし、神社と神と渡来人と古代史の話はにゃんとも複雑であります笑。実は秦河勝があの菅原道真や平将門にも匹敵するかもしれないぐらいの祟りをもって坂越に訪れた可能性もあるようでにゃんともかんとも奥深いっ
また、獅子舞っていったい何なの?という疑問も秦氏を追いかけていくことで徐々に分かっていくような気がしてきました。もちろん獅子舞には江戸時代に一般庶民が「文化」を堪能できるほど経済的な豊かさを持ちえたからこそ発展しただとか、豊作の祈りであるとか、祭りが盛んな地域と民俗性だとか、娯楽として若者に消費された側面があるだとかそういったことも面白いとは思うのですが、獅子や猿田彦の舞にはどのような意味があったのかといった一端が分かっていくかもしれません。
古代史の魅力と言われれば、事実かどうかはさておき解釈と妄想の余地が残されているところが面白いのかもしれません。近代史だとなかなかそうはいきません。
たまに時間を見つけては「秦河勝って誰やねん問題」に取り組んで参りまする。
つづく。