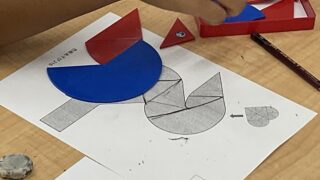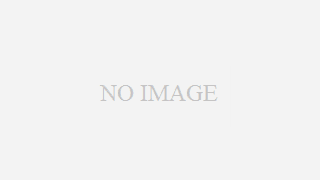目次をタップすると、見本動画まで移動します。
目次に戻りたい場合は、画面右下に表示される「トップへ↑」もしくは「↑」をタップして下さい。
じゅげむ
ごんぎつね 【新見 南吉】
ごんぎつね➀
開始位置15:10
ごんぎつね➁
注文の多い料理店 【宮沢賢治】
読んでみれば、ただただ「山の中にはいっていき趣味で狩りをする紳士が、山猫に騙されて食べられそうになる」というだけのお話ですが、
深く考えれば、いろいろ考えてしまう作品です。
それこそ、「平成狸合戦ぽんぽこ」のような「人間の業にあらがいながら、そんなこと無理だよね」といったこと感じるのか、結末の曖昧さでいうなら「もののけ姫」のように喩えることも出来ます。
登場人物が、猟を生業とした猟師ではなく「軍隊の格好をした紳士」であること、塩をぬるまでの巧妙な仕掛けの順序、を考えたときに、山猫によるただのいたずらとも言えず、最後の1説を考えると「間抜けなツメが甘い山猫の話」とも考えることも出来ず、、、
いろんな読み方が出来るのではないかと思います。
ご興味あれば是非、全編お読み下さい。
どんぐりの山猫 【宮沢賢治】
どんぐりの山猫➀
どんぐりと山猫➁
セロ弾きのゴーシュ 【宮沢 賢治】
開始位置 11:20
走れメロス 【太宰治】
走れメロス➀
走れメロス➁
開始位置 4:15
走れメロス③
開始位置 6:35
走れメロス④
開始位置 15:30
走れメロス⑤
開始位置 18:15
走れメロス⑥
開始位置 21:06
走れメロス⑦
開始位置 27:07
走れメロス⑧
開始位置 31:15
走れメロス⑨
開始位置 34:10
走れメロス⑩
開始位置 36:01
坊っちゃん 【夏目漱石】
坊っちゃんの続きが気になる方はこちらへ↓

坊っちゃん 【夏目漱石】
さて、今回は冒頭部分があまりにも有名な坊ちゃん。赤穂市の中学生が使用している国語の教科書にも掲載されています。しかし、...
開始位置 00:15