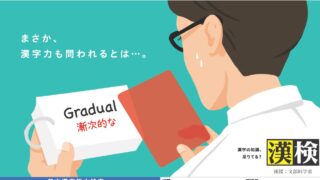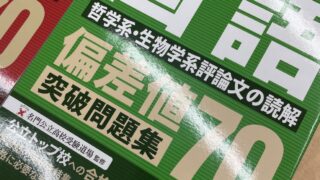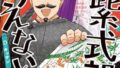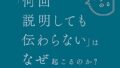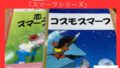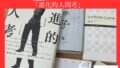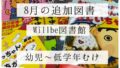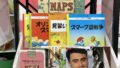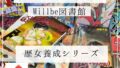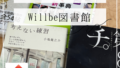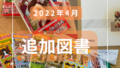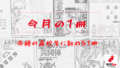赤穂市の個別指導塾Willbe塾長の光庵です。
毎月、小学生や中学生が読んで、目先の点数ではなく、広い世界を知るという意味で賢くなりそうな本を集めて本棚においております。
また、将来の夢や目標は「偶然の出会い」によるところが大きいです。誰といつ出会うのか?それは運です。違いがあるとするならば、出会いと求めてにいく習慣があるかないかでしょう。
一方で、人は「イメージ出来ない事」は実現できません。
出会いなき「将来の夢」「自己相対化」の授業は不毛なものとなるでしょう。
賢い子は、世の中を知っている。
今回は、エリーザベドです。
偶然にも2025年7月のWillbe図書館は同年代を生きた2人の女性にまつわる伝記を購入していました。少し興味深いので最後に2人を簡単に比較してみます。
絶世の美貌を誇るオーストリア王妃
エリーザベト(エリザベート・フォン・ヴィッテルスバッハ、1837年~1898年)は、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の皇后として知られる人物です。
美貌と自由を愛し、厳格な宮廷生活に苦しみながらも、詩作や旅行に没頭しました。
愛称「シシィ」として親しまれ、悲劇的な人生も相まって現在も人気があります(どこで?)。晩年は精神的に不安定となり、スイスで無政府主義者によって暗殺されました。その波乱に満ちた生涯は、舞台『エリザベート』など多くの作品で描かれています。
エリーザベトと同時代を生きた日本人
| 名前 | 生年 | 没年 | 主な分野・功績 |
|---|---|---|---|
| エリーザベト | 1837年 | 1898年 | |
| 坂本龍馬 | 1836年 | 1867年 | 幕末の志士、薩長同盟の仲介者 |
| 西郷隆盛 | 1828年 | 1877年 | 明治維新の中心人物、西南戦争で自決 |
| 勝海舟 | 1823年 | 1899年 | 幕臣・軍艦奉行。江戸城無血開城を実現 |
| 福澤諭吉 | 1835年 | 1901年 | 『学問のすゝめ』著者、慶應義塾創設者 |
| 伊藤博文 | 1841年 | 1909年 | 初代内閣総理大臣、明治憲法の起草者 |
| 大久保利通 | 1830年 | 1878年 | 明治維新の立役者、近代国家体制の構築 |
| 木戸孝允(桂小五郎) | 1833年 | 1877年 | 長州藩出身、維新三傑の一人 |
| 中江兆民 | 1847年 | 1901年 | 「東洋のルソー」と呼ばれた思想家 |
エリーザベトが残したと言われている言葉
・私は髪の奴隷です。
・私は鳥かごのなかで身をすくめているカモメよ。
・私は愛なんていりません。私は喪服を着て、大きく白い翼で、妖精の国に帰りましょう。
・皇帝陛下の抱えるイタリアの問題が収まらなければ私は心を痛めてます。ですが、ハンガリーで問題が起これば私は生きていけません。
エリーザべトとサラ・ベルナール
| 項目 | エリーザベト | サラ・ベルナール |
|---|---|---|
| 生年 | 1837年(バイエルン) | 1844年(パリ) |
| 没年 | 1898年(61歳) | 1923年(78歳) |
| 社会的立場 | オーストリア皇后(君主の妃) | 舞台女優・劇団主宰(芸術家) |
| 愛称 | シシィ(Sisi) | 神の声を持つ女優(La Divine Sarah) |
| 性格 | 内向的・自由を求めた | 外向的・情熱的・自己演出家 |
| 主な活動 | 詩作・旅行・宮廷からの逃避 | 世界巡業・演劇・映画出演 |
| 悲劇性 | 宮廷に抑圧され、最期は暗殺 | 片足を切断しながら舞台に立ち続けた |
| 現代評価 | 悲劇的美と自由の象徴 | 舞台芸術とセルフブランディングの先駆者 |
時代の枠に捉われなかった女性/自由との戦い方
エリーザベトは皇后としての義務を嫌い、自由を追い求めてヨーロッパ各地を旅しました。しかし、どこまでいっても皇后に自由はなく、エリーザベトは徹底した美容や運動習慣、詩作を通して自我を保とうとしていました。
エリーザベトの自由は、名声を望まず、政治的教養・宗教的敬虔さ・忠誠・控えめな態度・家族第一の姿勢を含んだ「完璧な皇后」として完璧であらねばならないといった「逃れたい理想」に縛られながら、個としての自由を追い続けた自由です。「髪の奴隷」という言葉が重くのしかかります。
エリーザベトはその美貌でヨーロッパ中に知られましたが、年齢と共にその美しさを保ち続けることを強く求められました。その結果、過激なダイエット・運動・美容法に取りつかれ、「美しくなければならない」という幻想の囚人になっていきます。
「美」で評価されることは、同時に「美しくなければ存在を許されない」という恐怖を感じてしまいます。それが望んだ人生だとしても葛藤を持ちそうではあります。
エリーザベトの求める自由が内面的であるならば、サラ・ベルナールは外向きです。有名であることを自ら望み求めていきます。サラの自由は「理想を創り出す力」とも言えるでしょう。具体的には、サラは男役(ハムレットなど)も演じ、ジェンダーの固定観念を超えた存在にもなっています。
その存在を周囲に認めさせていたのが自己プロでユース力。
自伝や詩、手紙などを積極的に出版しており、「神の声を持つ女優」といった現代でいうなれば”キャッチコピー”も自ら作ったと言われており、周囲に自分を「紙の声を持つ女性」と言わせていたそうです。
また、病気で片足を切断したあとも舞台に立ち続け、「片足のハムレット」として“伝説化”されることを自ら演出したともいえます。
もう150年も前の話であるのに、現在のインフルエンサーと同様の手法です。こういうところに歴史を学ぶ意義があるのだと個人的には思ってしまいます。
あなたはエリーザベト派?サラベルナール派?
軽く2冊を読み通してみて、そういった感想を聞きたくなってしまいます。好みが分かれる2人ですよね。同時に、映画「プラダを着た悪魔」を見た高校生の感想を思い出していました。
「自分のやりたいことをやるって辛いことなんですね。」
そうかもしれません。
プラダを着た悪魔では、登場人物を「やりたいことをやらないと決めた人」「やりたいことをやり続ける人」に分けることも出来ます。
どちらを選択しても構わないのですが、小学生/中学生達には、様々な価値観、広い広い世界を感じることのできるキッカケを求めてに言って欲しいな。
本当はもっと違うことをやりたいと思うのですが、塾ですから、ささやかに本を大量においておきます。
Willbe 図書館