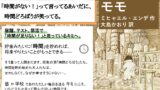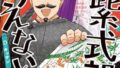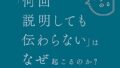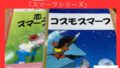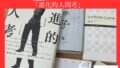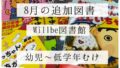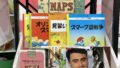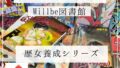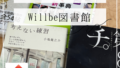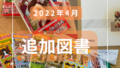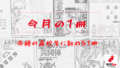こんにちは
赤穂市の進学個別指導塾Willbeの光庵(こうあん)です。
入試は得点ゲームの個人競技であるため、結果や点数といったものに拘らなければなりません。
しかし、一方で「学び」というものを考えれた時に「得点ゲーム」という側面だけではいけないように思います。
ゲームとしての勉強は否定はできず「教養」「知識」「ゲーム性」のバランスは必要なのだと思います。
そこで、今回は「勉強の哲学 来るべきバカのために」です。
勉強の哲学 来たるべきバカのために 増補版 (文春文庫) 【千葉雅也】
前回の「東浩紀」さん同様に、千葉さんの知らない本を見かけたら私は買ってしまいます。
賛否や好き嫌いが分かれてしまう人かもしれませんが、
好き嫌いが分かれる人こそ本物であるような気も致します。
↑前回↑
↓こちらの内田樹さんの知らない本を見かけたら買ってしまうのも同様です。
テーマの要約
「勉強の哲学 来たるべきバカのために」のざっくりしたテーマは、
勉強ができるようになるためには、変身が必要だ。
勉強とは、かつての自分を失うことである。
深い勉強とは、恐るべき変身に身を投じることであり、
それは恐るべき快楽に身を浸すことである。
そして何か新しい生き方を求めるときが、
勉強に取り組む最高のチャンスとなる。
——————
【要約】『勉強の哲学 来たるべきバカのために』■ 勉強とは「ノリ」を壊すこと
- 私たちは日常、「ノリ」(空気、慣れた思考パターン)に乗って生きている。
- しかし勉強とは、そのノリから距離をとり、自分の世界を「異化」していく行為。
- ノリを壊すことで、これまでの自分が変化する。これが「勉強による変身」。
■ 勉強の4段階(脱ノリのプロセス)
- ノリノリ期:何か新しい知識に出会ってワクワクする時期。
- ハマリ期:興味が深まり、特定分野にのめりこむ。
- シラケ期:飽きや虚しさを感じる。勉強が面白くなくなる。
- パラノ期(病的なこだわりの時期):自分なりの問いを持ち、新しい思考様式を切り拓く。
→ この4段階を繰り返すことが、思考の深化であり、真の勉強である。
■ 「来たるべきバカ」とは
- 常識的な知識や文脈から逸脱する「逸脱者」=バカ。
- しかしそれは単なる無知ではなく、新しい思考・世界を切り開く可能性を秘めた「来たるべき存在」。
- 勉強とは、この「バカ」になることを恐れず、自分を変える勇気を持つこと。
■ 勉強を「自分づくり」としてとらえる
勉強は「何かを得る」より、「何かを失う(過去の自分を手放す)」こと。
資格取得や知識獲得ではなく、「自分の思考スタイル・生き方を変えること」が勉強の本質。
といった感じです。
読んでみたものの、
どんな子に、
どういうタイミングで、
あそこに「勉強の哲学 来たるべきバカのために」って本があるよ~
とイメージがわかなかったので、紹介することなくお蔵入りしてしまうかも知れません笑
勉強を堅苦しく思わないで欲しい
結果が求められるし、競争することで傷つくこともあります。若いうちに傷つくことに慣れておく必要もあるのだろうと思うのですが、勉強ってそういうものではありません。
このままではいけないっと思った時や3年先の未来を少し変えてみたいと思った時にやることが勉強ですし、勉強が習慣になっている人は、スピードの速い世の中で、何が大事なのかを決めていけるとも思っています。
所謂「勉強」も大事であるし、大人になっても勉強を続けて欲しいと思うのです。
モモ琉にいうなれば、意味や効率なんて考えずに淡々と進めて欲しいものも勉強です。
Willbe 図書館




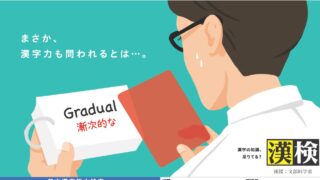


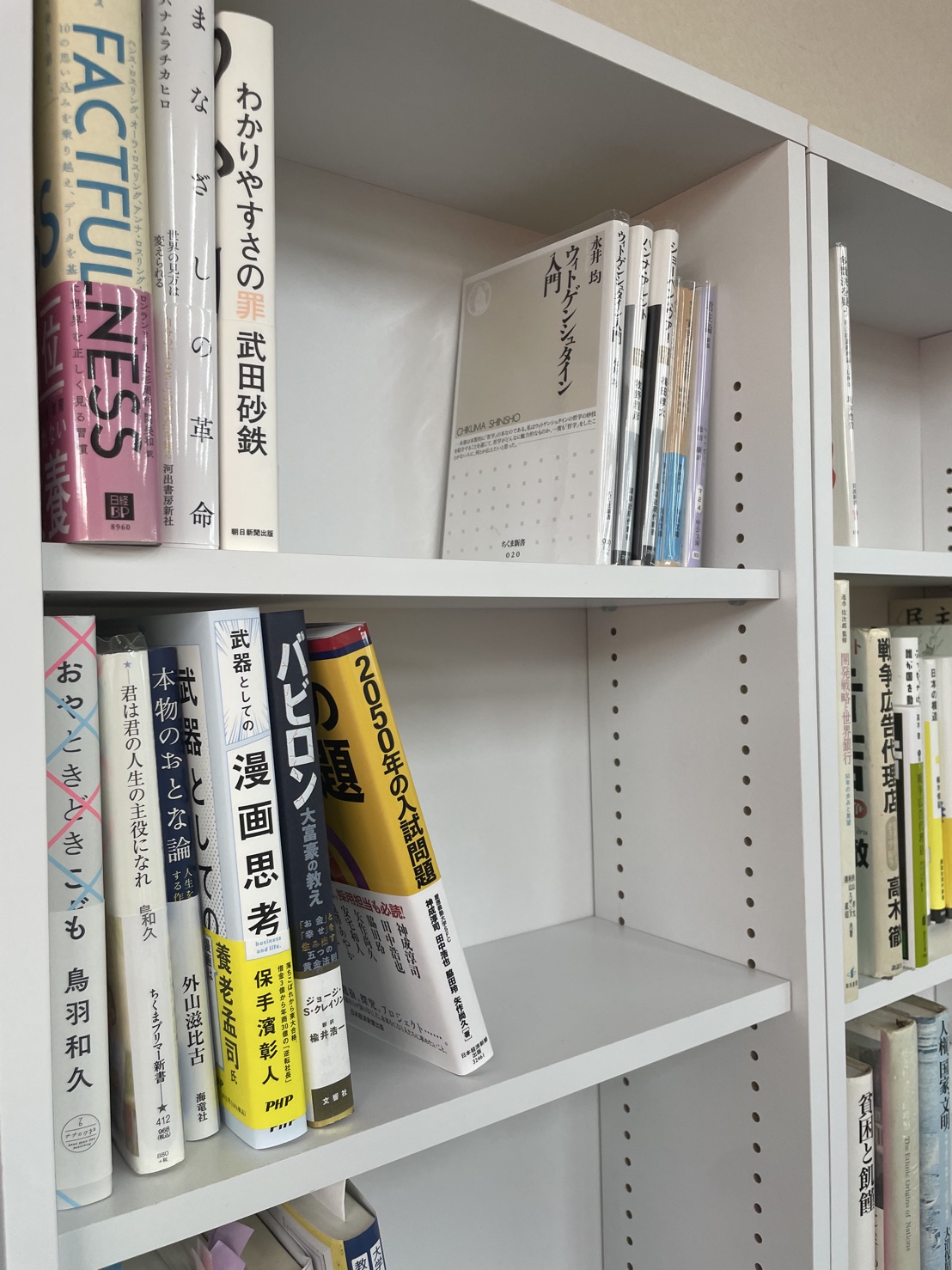
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477b908e.d707cdf5.477b908f.7beb4baa/?me_id=1213310&item_id=19897215&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4639%2F9784167914639_1_7.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)